筋トレあるある 筋トレ短歌 佳作20選 淡く切ない筋肉愛から怒りの筋トレまで網羅!!
今まで紹介してきました。筋トレ短歌の内で特に優秀だった二十首を紹介します。
- 一首目 紫百式部
- 二首目 俵マチョ
- 三首目 小林ISSA
- 四首目 平目筋源内
- 五首目 与謝野亜筋子
- 六首目 清小円筋納言
- 七首目 正岡メソッド
- 八首目 石川宅トレ
- 九首目 筋子みすゞ
- 十首目 夏目僧帽筋
- 十一首目 柿本マシュマロ
- 十二首目 ダサい治
- 十三首目 清小円筋納言
- 十四首目 森横柄
- 十五首目 よせ蕪村
- 十六首目 いい!!直弼
- 十七首目 山上オクラ
- 十八首目 江戸川さんぽ
- 十九首目 在原もり平
- 十九首目 大伴力持ち
- 二十首目 北大路魯山筋
- その他の記事はこちら
一首目 紫百式部

二首目 俵マチョ
三首目 小林ISSA
「チートデイ 自分自身に 言い聞かせ 初めて二日 減量期の夜」
・作者 小林ISSA
江戸三大歌人の一人。代表句「体脂肪率3%蛙 負けるなISSA これにあり」はカエルのボディービルコンテストで聞いた掛け声をもとに読まれた句。
・解説
季語はありません。チートデイは減量期の係り結びになっており減量期を強調しています。
チートデイとは減量期に代謝が落ちないように代謝量以上にカロリーを摂取する(人によっては好きなものをお腹いっぱい食べる)減量テクニックですが、通常チートデイは10日から14日程度に一日設定することが多いです。
今回の句では減量することを決意し実際にやったみたもののどうしてもカロリーの高いものを食べたくなってしまう人間の本能と自分に負けてしまった悔しさを表現しながらも減量は続けていく意思を感じさせる、ISSAらしい情緒豊かな句になっています。
四首目 平目筋源内
「足トレを やるぞやるぞと 思う昨日 やめよやめよと 言い訳の今日」
・作者 平目筋源内
江戸時代の俳人、発明家など多才な顔を持つ人物。静電気発生機「エレキテル」を復元した。
「エレキテル」は江戸のSIXPADとして多くのトレーニーの筋肉を震わせ、筋肥大させた。
また、「土用の丑の日」にクレアチン(注1)を摂取する習慣を作ったのも源内である。
(注1)クレアチンは筋トレ時のパワーを一時的に上げるサプリメントです。接種することで筋肉が一時的に張る副効果が出ることがあります。
(下記リンク先からご購入頂きますと八べぇに若干の紹介料が入ります。紹介料はレビュー用のサプリメント購入費用に充てさせて頂きます。)
・解説
足のトレーニングはキツイため明日は頑張ってやるぞと思っても、当日になって「膝が痛いなぁ」、「背中のダメージが抜けてないなぁ」と言い訳を考えてどうしても後回しにしがちである。解説を担当している八べぇも足のトーニングサボってしまうことが多い…
チキンレッグ(注1)はトレーニー共通の敵のため駆逐していく必要がある。
(注1)上半身ばかり筋トレをして上半身は大きいが下半身が発達していない状態。
五首目 与謝野亜筋子
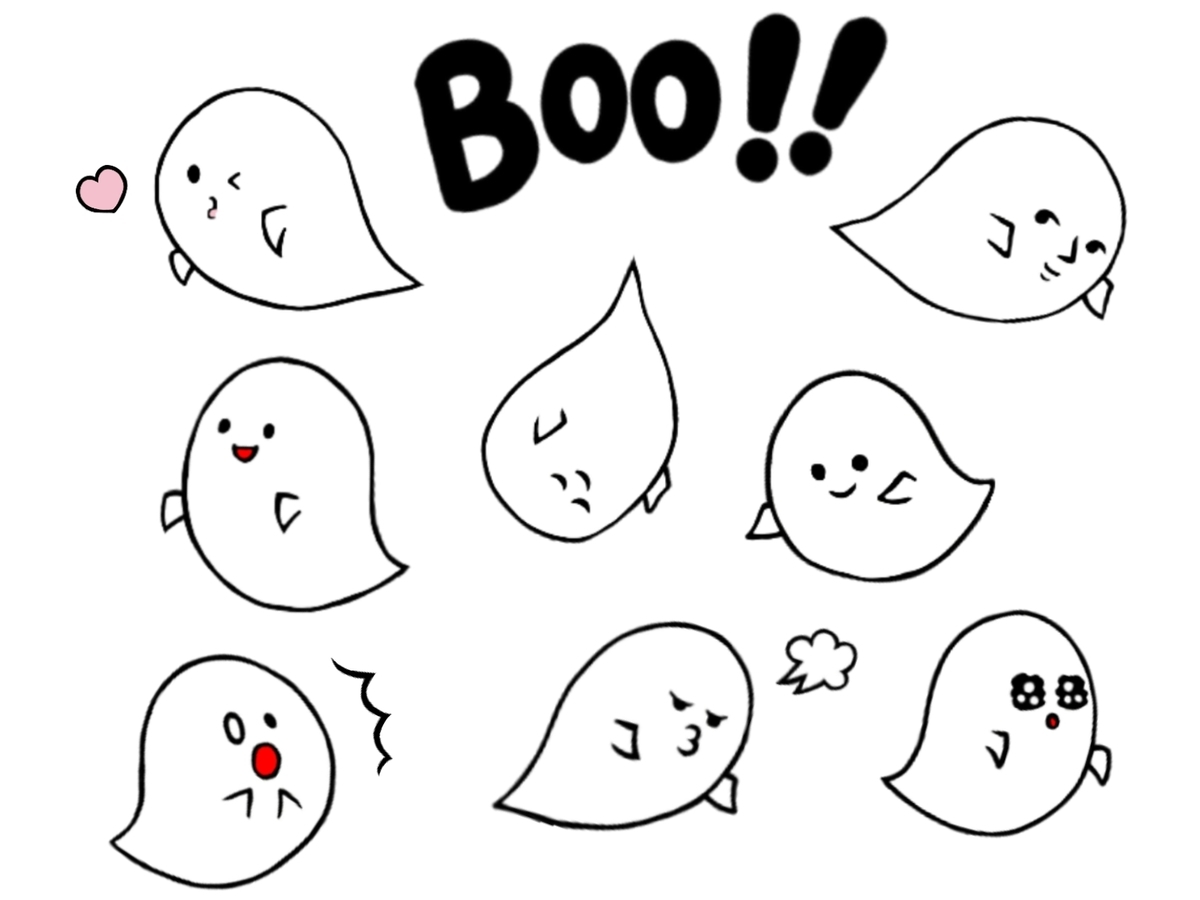
解説者である八べぇも腹筋中にどうしてもオナラが出てしまったことがあるが体が少し浮くぐらいの強力な威力であった。
六首目 清小円筋納言

・作者 清小円筋納言
・解説
最近太ってきたからなぁダイエットしなきゃという女中に筋トレしたらと言った際の女中の態度にキレ散らかした一句。
今でこそ女性の筋トレが一般的になってきたが一昔前まではムキムキになっちゃうから筋トレイヤだぁという女性も多かった。
体を大きくしようと相当な覚悟をもってトレーニングしても少しずつしか大きくならないのにその程度の覚悟の人間がデカくなるわけがない。
じわじわ怒りが湧いてくると共に筋トレしたらって言わなければ良かったと自分字自身の発言に少し後悔するのであった。
こんな経験をしたトレーニー諸兄も少なくないのではないだろうか。
七首目 正岡メソッド

・作者 正岡メソッド
・解説
重たい物を運んで報酬を得ることは一般的であるが我々トレーニーは逆にお金を払って重たい物を持ち上げに行く。この点は大きな矛盾である。
筋肉の魅力に取り憑かれた我々にとってはその矛盾に気付きながらもトレーニングを辞めることは出来ない。我々にとって筋肉とはどんな犠牲を払ってでも手に入れるべき価値を持ち我々自身も価値を追い求める探究者であり冒険者なのだというトレーニーの思いを込めた一句である。
八首目 石川宅トレ

・作者 石川宅トレ
・解説
使いたいと思ってるマシンにふと目をやると他の人が先に使っていることがある。
そのこと自体は順番なので仕方がないが急いでいる時に限って先に使ってる人がスマホばかりいじっていてほとんどトレーニングしていない。
セット間の休憩どんだけ取ってんだよと腹が立ってくる。
マシンを椅子か何かと勘違いしているのだろうか。マシン使うなら筋トレしろ筋トレしないならマシン使うなともやもやする気持ちを綴った一句。
皆さんイライラすると筋肉に良くないストレス物質のコルチゾールが出るので優しい気持ちで生きていきましょう。
九首目 筋子みすゞ

・作者 筋子みすゞ
いやいや、あんためちゃくちゃ汗かいてたやんマシンにも汗汁染みてるわと思いながら次に使う自分がマシンを拭く。マシン使ったら拭くのは筋トレの常識だろというモヤモヤした気持ちをマシンにぶつける姿を読んだ一句。
急いでいる時など忘れてしまうのはある程度仕方がないことだが次に使う人のことを考えてマシンなど使用後は必ず拭くようにしよう。
十首目 夏目僧帽筋
十一首目 柿本マシュマロ

・作者 柿本マシュマロ
・解説
ベンチプレスやデッドリフト、スクワットなどで自身の記録更新にチャレンジする際には自然とアドレナリンが出て気合いが入る。
今回の句は記録更新チャレンジ前の一呼吸入れているシーンを繊細な表現で切り取っている。
他人から見ても気合いの入り方や呼吸の仕方でこの人今日記録更新狙ってるんだなぁって感じとることが出来る。
解説者である八べぇは知らない人でも記録更新に挑戦している姿を見るとなんか嬉しくなってしまう。更新出来なくても心の中でナイスファイト!と応援している。
十二首目 ダサい治

・作者 ダサイ治
代表作である「筋トレ失格」は筋肉の大きさを求めるあまりシンソール(注1)に手を出した人間の壮絶な筋トレ道を描きセンセーショナルを巻き起こした。
海外などで二等筋だけ異常にデカいみたいな人いるよねぇ。
イチャコラは夏の季語。ギラついたは目の枕言葉。
ジムでトレーニングをしていると時々カップルで筋トレしている人達に総合する。
それ自体は全然良いのだが、大体そういう時の男ってイキっているので「お前そんな重量も上がらないの?俺なんか〇〇」とか言うことが多い、それに対して女は「えー〇〇君すごーい」と黄色声。ムカムカしてくる。
その腹立たしい感情と女子と筋トレ出来て羨ましいぃぃという感情から生じた怒りと性欲をパワーに変えてダンベルにぶつけて昇華させている様を描いた一首。
ちなみに男性は性欲が高まると男性ホルモンであるテストステロンが多く分泌されるようになります。テストステロンには筋肉の合成を促す作用があるため筋トレ中に性欲を高めるのは悪いことではないらしい...
十三首目 清小円筋納言

・作者 清小円筋納言
2回目の紹介。平安中期の女流作家。
代表作「ベンチ草子」は宮中で開かれた紫百式部とのベンチプレス対決までのトレーニングの記録や減量中の食事などが詳細に記載された随筆。
本書には「春はあけぼの」つまり春は夜明け頃にトレーニングした方が良いなど四季ごとのトレーニング時間についても記載されている。
・解説
冒頭に「いとおかし」が使われているが「をかし」と異なり「変だ」、「不思議だ」という一般的な「おかしい」の意味で使われている。
筋トレを初めてある程度筋肉が発達してくると今までと同じトレーニングでは筋肉が慣れてしまい十分に刺激することが出来なくなる。
今回の句は前日にトレーニングをしたが筋肉痛が全くこないなぁ負荷が少し足りなかったかなぁという残念がる感情を表現している。
十四首目 森横柄

・作者 森横柄
明治、大正の小説家、評論家、軍医、官僚など非常に多彩な人物。
体がデカくなったことによって店員などに横柄な態度をとっていることを友人から指摘され、自分自身の行動を振り返る。その後、「デカく、正しく、慎ましく」をモットーに生きるようになる。
・解説
ジムで見かけない新参者がトレーニングしているとどうしても体をマジマジと見つめて「肩の大きさはどうだ」、「大胸筋はそこそこかなぁ」など勝手に相手の筋肉をスキャンして自分と比較してしまう。
特に自分と同じような大きさの人だとライバル心に火がついてしまい「あいつ俺もよりも重量挙げているぞ。」などにトレーニングの内容も気になってしまいなんか悔しくなってしまう。今回の句はそんなトレーニーの気持ちを表現している。
解説者である八べぇもトレーニングを始めた頃は新しく入った人のことを意識しまくっていたが、最近は自分と同じくらいの大きさの人間にしか反応しなくなった。
十五首目 よせ蕪村

・作者 よせ蕪村
江戸時代中期の日本の俳人、文人画家。
筋肉が痛みのシグナルを出してもトレーニングを全く止めることなく自分の意思とは関係なくバーベルを落とした時にトレーニングを止める、ジャックハンマーレベルの非常にストイック性格の持ち主。
俳号はそんな蕪村のストイックさを友人に止められたことからついた。
・解説
モテるために筋肉をつけようとして筋トレを始める人も少なくない。
目的こそモテるためだが、トレーニングをはじめて少し経ち筋肉がほんの少し大きくなっていることに気が付くと筋トレにどハマりしてしまった。
筋肉が大きくなればなるほど筋肉への愛が大きくなっていく。段々、モテるとかどうでもいいわ筋肉の方が可愛いし大切だわというストイックなトレーニーの気持ちを表現している。
一般的に細マッチョ程度であれば女性に嫌がられないことが多いが大きくなり過ぎると気持ちがられることの方が多いようだ...
十六首目 いい!!直弼

「うっせいわ クソ大学生 集団で ベンチ大会 いつまでやんねん」
・作者 いい‼︎直弼
幕末の譜代大名。圧倒的バルクとカットを武器に「大江戸力肉比べ大会」(大江戸ボディービル大会)で優勝し大老に就任した。
当時日本は筋トレ鎖国を実施していたが直弼が強行的に日本の筋トレ開国へと導いた。
開国時に敵を増やし過ぎたため桜田門外で実施された力肉比べ大会では会場から「いい‼︎」と掛け声が出る程仕上がっていてが優勝を逃した。これがのちにいう「桜田門外の変」である。
・解説
直弼が大会へ向けた減量中に大学生がベンチを占領してベンチプレスをして最大重量を競い合っている。それ自体は全然問題無いのだが、「お前40キロしか挙がらんの?」と多少トレーニングかじってます的な奴がイキリ散らしている。うるせぇしただただ不快。
そしてそういう奴に限って大集団でベンチプレスの重量大会をしており長時間占領してベンチが開く気配がまったくしない。
今回は直弼がジムでムカついた光景を詠んだ一句。
十七首目 山上オクラ

「反射する ショーウィンドウを 利用して 自分の筋肉 状態確認」
・作者 山上オクラ
伝来して間もないオクラを使った減量メニューを和歌に乗せて発信し当時の公家トレーニーに広く浸透した。
当時の人気はすさまじかったが掲載確実とまで言われた百人マッチョへの掲載は惜しくも逃している。
・解説
ウィンドウショッピングなどでショーウィンドウに反射した自分の姿を見ると歩きながらでも筋肉にクッと力を入れてデカさを確認してしまう、そんなトレーニーの性を詠んだ一首。
もちろん服屋などの鏡でも同様の筋肉チェックをしてしまうが鏡だとはっきり見え過ぎてしまうい、ここ弱いなぁという気持ちが出てくるため窓ガラスの反射程度にボヤけていた方が楽な気持ちで確認が出来る。
解説者である八べぇも良くやってしまうが他人からはイキっているようにしか見えないため周りの目には気を付けて筋肉確認するようにしよう。
十八首目 江戸川さんぽ

「有酸素 大切なのは 分かってる やる気がしない しぼむ気がして」
・作者 江戸川さん歩
大正・昭和期の作家で本格的なトリックを駆使した推理小説で日本の推理小説を牽引した人物。
超人的なマッスルコントロールを用いて巧みな変装をする怪盗を少年探偵が追い詰める「怪人二等筋相」が代表作。
また、ランニングマシンがなかった当時、散歩することで有酸素運動する減量する方法を提案し広くトレーニング業界に受け入れられた。
・解説
ランニングなどの有酸素運動は消費カロリーを増やし脂肪の代謝を促すため減量する上では非常に効果的な運動である。筋肉をデカくする際には自身の総代謝以上にカロリーを摂取しないと筋肉は大きくならない。また、摂取カロリーが不足すると筋肉を分解してしまうため、増量期は有酸素運動をしないというトレーニーも少なくない。
ただ、有酸素運動には減量効果以外にも心肺機能の強化などのメリットも期待出来る。
有酸素運動の効果は分かっているがしぼむことを気にしてやる気が起きない増量期トレーニーの葛藤を詠んだ一首である。
解説者である八べぇは有酸素運動は汗かくし疲れるから大っ嫌いである。
十九首目 在原もり平

「聞かれると とっさに盛って はなしちゃう プラス5キロの 最大重量」
・作者 在原もり平
平安時代初期から前期にかけて活躍した、貴族、歌人。
ベンチプレス六歌仙の一人。
すぐに話を盛るクセがあり、それを見透かされてベンチプレス勝負をした際には重量を盛ってコールしてしまい持ち上げることが出来ず記録無しという不名誉な結果になってしまった。
・解説
良く筋トレをしているというと他人に言うと「ベンチプレス何キロ挙げれるの」と聞かれることが多いがその際にとっさ5キロぐらい持てる重量を盛って話してしまうそんなトレーニーの小さな見栄を繊細に表現した一首。
最大重量は5キロまでは盛っていいが5キロを超えて10キロなど盛るとウソになるので注意が必要である。
解説者である八べぇも最大重量が95キロの頃はなんか恥ずかしかったので100キロと言ったが最近は盛る方が恥ずかしくなってきたため盛るのを止めた。
十九首目 大伴力持ち

「罪悪感 筋トレサボると 訪れる 自分自身に 悪いことした」
・作者 大伴力持(おおとものちからもち)
和歌で有名な大伴家の中でもっとも力持ちな人物で当時始まったばかりのパワーリフティング(スクワット、デッドリフト、ベンチプレスの合計重量を競う)では6石(900キロ)という当時からすると驚異的な数値を出している。
なお、最新の研究では大伴はパワーリフティング計測時にアナボリックステロイドに類似する製品の薬品を常用していた可能性を指摘されている。
・解説
筋トレがある程度習慣になってきたトレーニーにとって日常生活の中で筋トレをすることが当たり前になっているため筋トレをしない日はむしろ筋肉に悪いことをしてしまった...裏切ってしまったという罪悪感を感じてしまう。
出張が多いトレーニーなどは各出張先に手頃なジムを見つけて出張先でもトレーニングを怠らないようにしていることも少ない。
筋トレを非常に頑張っている大伴の筋トレをサボってしまった罪悪感が表現された一首である。
二十首目 北大路魯山筋

「ヤバかったぁ ベンチプレスで ヒヤリハッと セーフティーバー 指差し確認」
・作者 北大路魯山筋
大正から昭和にかけて活躍した芸術家。
陶芸や書道、料理家、美食家など非常に多彩な顔を持つ。
田んぼのプロテインと呼ばれるタニシを硬くなるのを避けるために生煮えの状態を好んで食べており、タニシに寄生していた肝吸虫に感染したことが原因で亡くなっている。
・解説
ベンチプレスは夏の季語である。
ベンチプレスで最も危険かつ起こりやすい事故の一つがバーベルを体に落としてしまうことである。実際に首にバーベル落としてしまい死亡事故も発生しているためベンチプレスをする際に最も気を付けなければならない。
作者である魯山筋がベンチプレスをしている際にギリギリを狙い過ぎてバーベルを落としてしまいヤバいと思ったが事前にセットしていたセーフティーバーのおかげで体に落とさずに済んだというヒヤリハッと体験をもとにセーフティーバーの設置を推奨する啓蒙的な一首である。
可動域が狭まるという理由でセーフティーバーを設置したがらないトレーニーも中にはいるがよほど軽い重量でない限りリスクが上がるだけなので設置することを強く勧める。
その他の記事はこちら
最近閲覧数が落ちて若干萎えていますので良かったら他の記事も見て頂けるとモチベーションが上がります。お願いします...
・コロナウィルスワクチン接種して筋トレしたら大変だった話
・筋トレモチベーション改善
・チキンレッグ根絶プロジェクト
本日の記事は以上です。

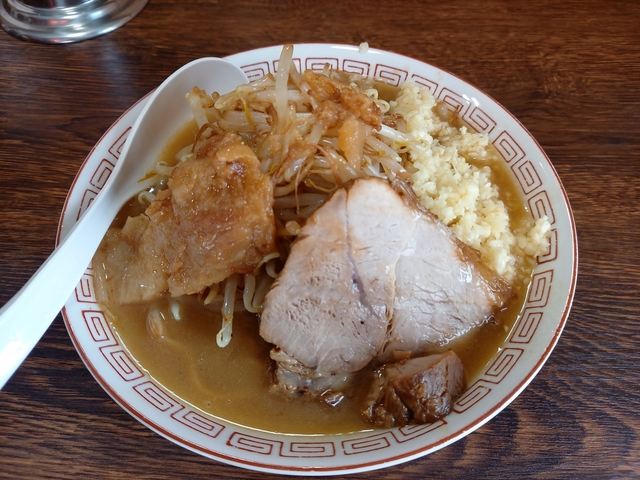


![IMG_4375-thumbnail2[1].jpg](https://kintorekoujyouiinkai.up.seesaa.net/image/IMG_4375-thumbnail25B15D-thumbnail2.jpg)